魔都・名古屋の最高峰にして世界に誇る山
ある人は魔都・名古屋の最高峰と称した。
ある人は名古屋が世界に誇る山と讃えた。
喫茶マウンテン。今やその名は誰もが一度は聞いた事があるだろう。
これは、マウンテンに挑んだ男たちの、壮絶な戦いの記録である。

マウンテンに行くためには、地下鉄鶴舞線・いりなか駅にて下車をして、しばらく歩かなければならない。上り坂を歩く。少しずつ傾斜が高くなってくる。中には、この暑さにやられて麓に辿り着くまでに疲れてしまう人もいるだろう。忘れてはならない。マウンテンとの戦いは既に始まっているのだ。
ほどなくすると、喫茶マウンテンの看板が姿を現した。
ここで、幾人もの冒険者たちが遭難したのだろうか。
それでも、マウンテンの持つ魅力に惹き付けられて、勇敢に挑戦する人は後を絶たないという。今日もまた、店の前には登山者が列を成していた。

地元のシェルパ(マウンテンに慣れた人のこと)によると、人気店だけに店外まで列ができている日も多いとか。しかし、「マウンテン」は喫茶店なのに長居をする店でないという。
喫茶店なのに、長居できない。
その理由を、私は扉を開けた瞬間に知った。
鼻を衝く異様な匂いは言葉にすることはできない。山に来たのにもかかわらず、新鮮な空気が欲しくなる。マウンテンがその名を一躍広める事になったのは、奇天烈なメニュー故だ。甘口のスパゲティ。辛口のかき氷など。それを毎日毎週毎月毎年作っているのだろう。普通の料理ではない匂いがこびりついているのも無理はない。7月の暑さと皆の熱気が空気を淀ませる。店の中ですら、汗が噴き出してくる。
店の外に出てきた人で「ああ、新鮮な空気があったー」と叫ぶ人もいた。
魔の山、進入
小さなテーブルがある席につき、注文を取る。
「甘口バナナスパ」
「甘口メロンパン風スパ」
「甘口抹茶小倉スパ」
全員甘口かよっ!
シェルパのガイドによると、初心者はこうした頼み方をしてよく遭難する(食べきれなくなる)そうだ。甘口で統一する頼み方は、マウンテンに慣れた人か、チャレンジャーか、罰ゲームか、何も知らない初心者と相場が決まっているそうです。慣れないのに甘口を頼む時は、味の違う救いメニューを用意しておくべし。
救いメニューの代わりとして、もしもの時の命綱、ウーロン茶を頼んでおいた。 名古屋の喫茶店では飲み物を頼むと、クッキーなどの品が付いてくる。それは、マウンテンでも例外ではない。気前が良い名古屋の喫茶店。

そして、「山」が運ばれてきた。
喫茶マウンテン名物、「甘口小倉抹茶スパ」だ。緑のスパの山の頂きに、雲に囲まれたかのようなクリーム、それを包み込む小倉の岩。そして、登頂した人が立てたかのようなフルーツが、旗のように翩翻と翻っているように見えた。
目指すは、遥かなる山の高み。
「バルディッシュ、行くよ」
「Yes,sir」
愛杖を手にした某キャラクターのように、気合いを入れる者がいる。それに答える者がいる。
そんな台詞が出る程、余裕でした。慢心でした。オタクでした。
山の天気は刻々と変化する
写真を撮り終わってから、口に運ぶ。味わう。
噂通り、ケーキのように甘いスパゲティだ。
この程度ならば、労せずとも登頂(完食すること)できるのではないだろうか。 だがこの時、私は自身が既に雪崩に巻き込まれていそうになることを知る由もなかった。山頂付近のクリームが溶解し、雪崩が発生している。まずい、このままでは登山直後に遭難してしまうのではないか。クリームを先に全て平らげ、最初の危機を逃れたかに見えた。やれやれ。
――霊峰マウンテン、思った程のものでもない。
一口、また一口と味わうように口に入れてゆく。ただ甘ったるいだけで、特に苦戦することもなく山頂へ向けて歩を進める。他の山の様子を見ると、すでに半分、五合目を越えているではないか。この時に既に水をあけられていたのだ。
味わってはいけない。熱を含んでいるが、一気に食すべし。
「ほれほれ、食ってみ」
「どれどれ」
「何て言うか、食欲を落とす味やね(笑)」
などと、和気あいあいと頂上へ向けて登山する。気分は、ハイキングだった。
山の天気は刻々と変化する。今は晴れでも、一時間後には暴風雨になるかもしれない。その言葉通り、ただの甘い食事だった抹茶スパが牙を剥いて襲いかかる。
マウンテンの遭難伝説は、事実だった。クリームをどかして、見えてきた緑の物体は、油にまみれている。いかな甘党でも、登頂を断念するのはこの抹茶のためだった。クリームや小倉は甘い。フルーツはさわやか。そして抹茶はほろ苦い。単品で食べるならば、おいしいはずなのに。どうしてこうも「混ぜるな危険」になるのか。五合目に到達した時点で、私は汗をかいていた。冷や汗を。
全員が無言になる。
誰もが甘口の山に苦戦しているようだった。
ふと、ひとつの思い出が脳裏に甦る。
それは2005年5月のこと。
大阪・日本橋のメイドカフェを一日で全店制覇しようとして、コーヒー、ケーキと食べ続け、最後に大人のお子様ランチで撃沈し、体調不良になった記憶が走馬灯のように流れていた。
そして、今、マウンテンで遭難しかけている私がいる。
「俺は何をやっているんだ? なんでこんな飯を食っているんだ?」
そんな投げやりな気分になっていた。
全然成長していません、この管理人。
それと、初心者は一人で危険な山登りをしてはいけません。こんな考えが頭に浮かびながら黙々と食べ続けることになるかもしれませんよ。
続々と食べ終わるのに
それでも歩みを止める者は誰もいない。全員が登頂を目指して、一歩一歩着実に進んでいた。
私の中で、甘口スパの評価は、ただ甘い食べ物から、トラウマになる食べ物へと進化していた。さすがは霊峰マウンテン。予想を裏切らず、期待を裏切らない。
「悪魔め……」
私は呟いた。しかし、眼前にいるのは白い悪魔でも「赤いあくま」でもない。それは、圧倒的な抹茶の苦みとクリームの甘口と油のハーモニーでのしかかる緑の悪魔。
緑の悪魔に体をぐるぐる巻きにされていると、天の頂から、声が聞こえてきた。
「登頂ー!」
「俺も食ったー!」
甘口バナナスパとメロンパンスパを制覇していた。
何っ! 私とは違い、ふたりの冒険者はウーロン茶を駆使しながら、熱いのを一気に駆け込み、瞬く間に登頂へと至ったのだ。私はまだ七合目。あんたら早すぎだろ。
「ちょっと席を外すから。その間に食べてもいいよ。と言うか、後全部食って(笑)」
私は一旦席を外して周囲を見た。近くのテーブルでは男女4人のグループが座っていた。
やーちんの一団と同じ甘口抹茶スパ、さらに鍋スパなどを頼んでいた。
ふ、素人が。お前ら後で地獄を見るぞ。
お前もな。
席に戻った時に事件は起きた。
頂上に高々と掲げられていたさくらんぼだけが、消えているではないか。
「あああ! なんてことを!」
「食べても良いって言ったやん」
「フルーツは砂漠におけるオアシス。山におけるザイル。甘口スパにおける救いメニューなんだよ」
甘口スパを制する方法として、先にフルーツや小倉を食べない、などの先人が生み出した知恵があります。
かつて南極を征そうとして、アムンゼン隊に先を越されたイギリスのスコット隊が南極点で見たのは、アムンゼンの自国、ノルウェーの旗だったという。期せずともその時の気分の10分の1でも味わうことになってしまった。
私はザイルも食料も失ってしまったものようだった。ウーロン茶を頼りに先へ進もうとするが、体に纏わりつく疲労感は尋常ではなかった。
「寝るなぁ! 寝たら死ぬぞ!」
「も、もうダメです隊長。下山しましょう」
「何を言う、頂上は見えているんだ。ここで引き返す訳にはサイト管理人の名にかけてもできない!」
何よりも、自ら過酷な山に挑んでいるのにもかかわらず、料理を残すのは人としてどうだろうか。とはいえ、抹茶スパから立ち上る臭気は私の食欲と体力を順調に奪っていた。命綱の残量を確かめる。もしもウーロン茶が切れた時、私の運命も潰えるだろう。
「バルディッシュ、大丈夫?」
「Recovery complete」
冷えてくると登頂は確実に難しくなる。
そんなことをやっている間があるなら早く食え。
再び、頂上へ向けて歩き始めた。
それでも引き寄せられる「味力」
頂上まで九合目。後三口で食べきれる所までやってきた。
依然として、この毒々しい食べ物は私をあざ笑うかのように見据えている。パスタに搦めたフォークをくるくると回す時間だけが延びてゆく。
ウーロン茶で喉の奥に流し込む。もはや食べ物の食べ方ではない。異物を無理矢理体の中に入れる方法だ。後、二口。気を抜くと足を踏み外して崖から落ちてしまうかもしれない。椅子に深くもたれ込んだまま、体を動かせなくなった。
登頂目前まで来て、遭難するのか?
恐らく、この抹茶スパは二度と食べられない。
次に食べる時があるならば、今回のトラウマが食欲を鈍らせて、間違いなく五合目あたりで遭難するだろう。
手を伸ばせば、届く所に栄光は待っているのに。私には遭難者と言う烙印か、サイト管理人におけるネタとしか判を押されないなのか。薄れゆく意識の中で、私は伸ばした手を掴まれる感覚を覚えた。
見かねた二人が、最後の二口を食べていた。そう、私は崖から落ちる瞬間、頂上で待っていた二人に腕を掴まれ、栄光の頂きへと引きずり上げられたのだった。

「ファイトーーーーーーー!」
「いっぱーつ!」
「よっしゃー! 登頂完了!」
隣の男女が、そして、甘口抹茶スパを頼んだグループが驚きの表情をこちらを見る。高々と空になった皿をかかげたならば、それが登頂の旗印になったかもしれない。
満腹の思いで、いや、万感の思いで下山し、マウンテンを後にする。ここ、マウンテンでは遭難しても再び山登りに来る人が後を絶たないと言う。数十年、人々を惹き付けてやまない奇天烈で不思議な味がそこにはある。あれほど大苦戦した抹茶にもかかわらず、一日経つと、また行きたいなと思う。どうやら私も、マウンテンの魅力に取り憑かれた一人のようだ。
喫茶マウンテン。
そこは今日も多くの冒険者たちが登頂し、遭難する悲喜交々のドラマが繰り広げられている、「味力」ある熱い戦いの場所なのだ。
関連リンク
■ 喫茶マウンテン / 喫茶マウンテン (@kissa_mountain) · Twitter
■ 喫茶マウンテンをめぐる冒険 / K‘s Station
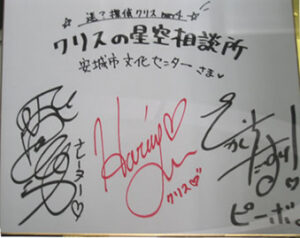







コメント